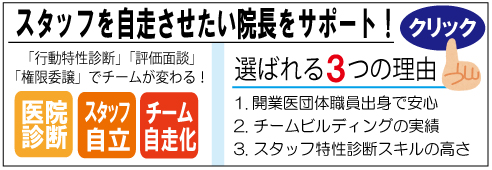「スタッフの〇〇さんは勤続10年だから安心」
「ベテランだから任せても大丈夫」
そう思っていた院長が、医院改革を始めようとして気づくのです。
「指示をしないと動かない」
「新しい取り組みに抵抗される」
「プロジェクトを任せても成果に繋げられない」
「若手との間に壁ができている」
“経験が長い=有能”ではなかった。
実は、これは多くの歯科医院が抱える共通のジレンマです。
では、経験の長さが必ずしも成果に結びつかないのはなぜでしょうか。
① 経験は「量」ではなく「質」で決まる
人は、同じ経験をしていても“成長する人”と“止まる人”に分かれます。
その差を決めるのは「経験の量」ではなく「経験の質」です。
心理学者デイヴィッド・コルブは「経験学習モデル」でこう述べています。
成長とは、経験を“振り返り・分析し・次の行動に活かす”循環である。
つまり、同じ10年でも、
・ただ“10年繰り返した”人
・“10年分の学びと経験を積み上げた”人
では、まったく違う能力になります。
歯科医院で言えば、
「ずっと診療アシストをしてきた人」が必ずしも「診療を最適化できる人」ではないということです。
この場合の責任は新たな分野に挑戦させたり、特定の分野を深掘りさせたりしてこなかった院長にあります。
能力は「学びの量(質)+経験の量(質)」で積み上がっていくからです。
② “惰性人材”が組織の進化を止める
ベテランが変化に抵抗する理由の多くは、「自分のやり方を否定されたくない」という心理です。
新しいやり方やシステム導入を提案すると、
「前の方がやりやすかった」
「そんなに変える必要あります?」
という声が出る。
しかしこの言葉の裏には、「自分の価値を守りたい」という防衛反応が隠れています。
院長がここで注意すべきは、“叱ること”ではなく、“構造を変えること”です。
惰性人材を叱っても動きません。
変わらざるを得ない環境と、安心して挑戦できる設計が必要なのです。
変化し続けない医院を作ってきたことが原因なので、変化する医院に作り変える必要があるのです。
この「変化し続ける環境づくり」は私の得意分野であり、クライアントの院長といつも作戦を立てて実行しています。
③ 「学び続ける構造」をチームに埋め込む
成長し続けるチームに共通しているのは、“学ぶことが日常業務に組み込まれている”ことです。
☑ 学びが仕組み化されている医院の例
・ミーティングで個人目標の進捗が定期的に共有され、学びが着実に身につく仕組み
・ペア学習制(ベテラン×若手)で互いに学び定期的に発表する機会がある
・症例検討やケースカンファで学んだことをチームで実践しレポートを提出
・5分間課題練習の時間が一日のスケジュールに組み込まれている(テスト有)
こうした環境では、経験の長さではなく「学習による成果」が評価されます。
それにより、ベテランも若手も“常に学び続ける文化”に染まっていくのです。
④ 経験が長いスタッフを“変化推進者”に変える方法
ベテランを否定する必要はありません。
むしろ、医院の“文化の担い手”として大きな力を発揮してもらうべきです。
ポイントは「役割の再定義」。
● ステップ1:知識を共有する立場に置く
「自分がやってきた方法を他者に伝える」機会を作ることで、経験が“価値化”されます。
そして自分が出来ていない事を学び直すキッカケとなりますので成長への刺激となるのです。
● ステップ2:変化の設計に関与させる
新しい取り組みを“決められる側”ではなく、“つくる側”に入れることで、主体性が生まれます。
その場合には新たな取組みにだけ注目するだけでなく、現状で出来ていないと感じることをベテランスタッフから引き出し、院長はその課題の解決をサポートするのです。
決して出来ていないことを駄目だししてはいけません。
● ステップ3:若手の成功体験を一緒に喜べる環境をつくる
ベテランが後輩の成長を喜べるようになると、チームの心理的安全性が高まります。
これにより、“守りのベテラン”が“育てるベテラン”へと変化していきます。
多くのベテランは「ちゃんと教えているのに出来ない」と若手を評価します。
しかし、「出来ない」のは育てる側のアプローチの問題であると気づいて、若手を「勇気づけ」出来るようにならなければ何も変わらないのです。
院長はこの時、若手の味方になるのではなくベテランスタッフの良き相談相手になる必要があるのですが、若手に退職されると困ると保護に走り状況を悪化させるのです。
⑤ 院長への問い:成長の循環を止めていないか?
1.「経験が長い=任せて安心(実は丸投げ放置)」と思い込んでいないか?
2.ベテランに“学び”や“挑戦”の機会を提供しているか?
3.若手が提案しやすい心理的安全性を作れているか?
4.ミーティングが“報告の場”で終わっていないか?
5.成果を出した人ではなく“学び続ける人”を評価しているか?
まとめ
経験の長さは「過去の成果」の証明にはなりますが、「未来の成果」の保証にはなりません。
医院を伸ばすのは同じことの経験量ではなく、成長に必要な分野の学習量(質)+経験量(質)。
そして、学び続けるチームを設計できるかどうかが、これからの院長の最大の経営力なのです。
次回は第4回:
「“患者満足度”より“患者理解度”を高めよ」
満足よりも患者の“納得と信頼”が医院経営を左右する時代。
数値では測れない「心の評価軸」をテーマにお届けします。
 |
|
 |
|
 |