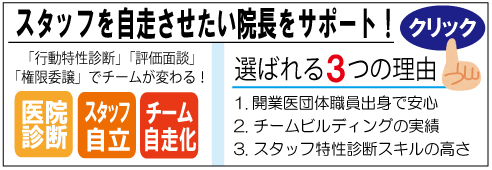今日は、歯科医院で起きやすい人間関係のすれ違いについて、
それを防ぐための「コミュニケーションデザイン(意図を持った会話設計)」の視点からお話しします。
チームがギクシャクするのは“悪意”ではなく“設計ミス”
多くの歯科医院では、次のような状況を耳にします。
・新人がなかなかスタッフの輪に入れない
・チーフに昇格したスタッフが孤立する
・相互理解が足りずにグループができる
・「院長 vs スタッフ」という構図になる
・仕事が特定の人に集中しても「つらい」と言えない
・中堅スタッフが「燃え尽き」や「青い鳥症候群」に陥る
これらは、個人の性格や相性の問題ではなく、コミュニケーション設計の欠如による組織的課題です。
つまり、「人の問題」ではなく「仕組みの問題」なのです。
信頼を生み出すための3つの“会話設計”
チームがうまく機能している医院には、共通して次の3つの「意図的な会話の設計」があります。
① 関係性を築く“感情共有”の会話を設計する
新人が孤立したり、中堅が迷ったりする原因の多くは、感情を共有できる場がないことです。
歯科医院では業務連絡や報告は多くても、「どう感じているか」を語る場はほとんどありません。
たとえば、
・週1回のショートミーティングで「今週の一言(Good & Challenge)」を共有する
・院長やチーフが“質問型”で会話を始める(例:「今週どうだった?」「何か気づいたことある?」)
こうした感情共有の仕組みがあるだけで、「自分を見てくれている」「受け止めてもらえる」という安心感と信頼が生まれます。
② 働く意味を再確認する“目的共有”の会話を設計する
中堅スタッフがモチベーションを失うのは、日々の仕事と医院の理念・目的のつながりが見えなくなるからです。
毎日の業務は同じでも、意味づけが変わるだけで活力は戻ります。
例:
「この患者さんが笑顔を取り戻せたのは、あなたの説明があったからだよ」
「医院全体で○○を大切にしていく。その中で、あなたの役割はこうなると思う」
院長が“理念と現場をつなぐ言葉”を意識的に発することで、スタッフは「自分の仕事が医院の未来に繋がっている」と感じられます。
これも、信頼を生む大切なコミュニケーションデザインです。
③ チームの課題を“対立ではなく共創”で語る会話を設計する
グルーピングや「院長 vs スタッフ」という構図が生まれる医院では、課題を話し合うときに「誰が悪いか」に焦点が向きがちです(原因志向)。
しかし、信頼を育てる医院では、
「どうすればもっと良くなるか?」
という“未来志向の会話”をします(目的志向)。
たとえば、月1回のミーティングで、
「課題共有」ではなく「改善アイデア共有」にフォーカスする。
・“誰が”ではなく、“何が起きたのか”
・“責任追及”ではなく、“仕組みの改善”
こうした会話を積み重ねると、医院全体が「協力して創る文化」に変わっていきます。
エッジのあるチームは“建設的な衝突”を恐れない
前回お伝えした「心理的安全性」は、意見を出しやすい土壌です。
そこに「信頼に基づく建設的な衝突」が加わることで、チームは機能します。
つまり、
“心理的安全性”はチームが機能するための土台、
“信頼に基づく衝突”はチームが進化するための推進力。
意見がぶつかることを避けるのではなく、違いを対話によって価値に変える文化こそが、真に強い医院を作ります。
チェックリスト:信頼を生む会話設計ができているか?
|
チェック項目 |
Yes / No |
|
スタッフが「感情」を共有できる場が定期的にある |
|
|
院長やリーダーが理念・目的を言葉で発信している |
|
|
課題を話すときに「誰が悪いか」ではなく「どう良くするか」で議論している |
|
|
新人や中堅が“孤立しない仕組み”を意識的に作っている |
|
|
チーム内で異なる意見が「成長の機会」として扱われている |
まとめ:信頼は「自然に生まれる」ものではなく「設計する」もの
信頼関係が自然に育つと思っている医院は、気づけば“静かな分断”を抱えています。
信頼とは、
・感情を共有できる関係
・目的を共有できる会話
・課題を共に解決できる文化
これらを意図的にデザインすることで初めて形になる。
医院経営における“会話の質”が、医院全体の“信頼の質”を決めるのです。
ひとこと
信頼は「時間」ではなく「設計」で築くものです。
偶然に頼らず、意図を持って関係性をデザインする医院は、離職も少なく、チームの幸福度も高い。
チームはデザインの仕方次第で輝くのです。
 |
|
 |
|
 |