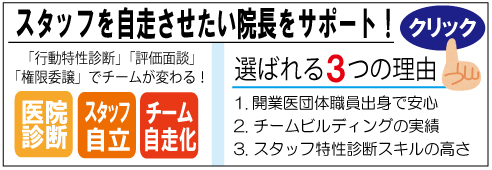最近、「求人を出しても全然応募が来ない」「入ってもすぐ辞めてしまう」という相談を多く受けます。
確かに、人口減少・少子化・賃金上昇という大きな波の中で、人材確保は年々厳しくなっています。
しかし私は思うのです。
「本当に“人がいない”のではなく、“人が活かされていない”のではないか?」
この構造的な問題を見落としてしまうと、いくら採用費をかけても結果は変わりません。
今回は、歯科医院が直面する「人手不足」の本質を、“仕事設計”という視点から見直してみましょう。
① 求人を出しても応募が来ない本当の理由
多くの医院では、求人票に「明るい職場です」「チームワークを大切にしています」と書いています。
しかし、応募する人はそれを“言葉”としてではなく、“構造”として見ています。
・仕事内容が明確に分かるか?
・成長していくイメージを持てるか?
・誰とどんな役割で働くのか?
つまり、応募者が求めているのは「安心して自分の力を発揮できる構造」です。
ところが、業務内容が曖昧で、役割の境界が分かりにくい医院ほど、入職への心理的ハードルが上がります。
魅力的な医院とは“環境の設計が見える医院”なのです。
② 「辞める理由」の8割は“仕事そのもの”にある
多くの院長が「人間関係が原因で辞めた」と感じています。
たしかに表面的にはそう見えます。
しかし、厚労省やギャラップなどの国際的な調査では、
離職の主因の7〜8割は「仕事内容への不満」や「成長の実感の欠如」に起因することが明らかになっています。
例えば――
・役割が曖昧で、自分の判断で動けない
・自分が何を期待されているか分からない
・改善点が多いと感じるが権限がなく実行できない
・スタッフ間で話し合う機会が少なく部署間でギクシャクしている
・院長の方針とチーフの指導がズレている
・後輩に指導する機会が増えたが、自分の学びの機会が少ないと感じる
こうした“仕事設計の不備”が、人間関係の摩耗を生み出します。
つまり、「人間関係で辞めた」は構造の結果であって、原因ではないということです。
③ 「意味のある仕事デザイン」が人を動かす
人が長く働く理由は、「給料」や「職場の雰囲気」だけではありません。
それは、自分の仕事に“意味”を感じられるかどうかです。
心理学者リチャード・ハックマンの「ジョブ・デザイン理論」では、人がモチベーションを感じる仕事には5つの要素があるとされています。
1.多様なスキルを活かせる
2.仕事の全体像が見える
3.社会的な意味を感じる
4.自律的に判断できる余地がある
5.成果がフィードバックされる
歯科医院で言えば、
「自分の関わりが患者の健康維持につながっている」
「自分の判断で改善提案ができる」
「チームの成果が数字や患者の笑顔として実感できる」
そう感じられる構造をつくることが、定着率を劇的に変えます。
④ チームを「補う関係」から「掛け算する関係」へ
多くの医院では、チームを「お互いの不足を補う関係」として設計しています。
しかしこれでは、誰かが欠けるとバランスが崩れ、余裕のない組織になってしまう。
これからは「掛け算する関係」――つまり、
それぞれが強みを発揮し、役割が重なり合って新しい価値を生む構造を設計することが重要です。
たとえば、
・歯科衛生士が患者教育をリードし、受付がフォローアップの電話を担当する
・ドクターが治療説明を行い、スタッフが患者の行動変容を支える
その設計が「患者の継続来院」という成果を生んでいるかを毎月確認し、話し合いながら連携方法と仕組みを改善し続ける。
このように社会的に意義がある「役割をつなぐデザイン」があると、仕事の意味がチーム全体に伝わり、自然とモチベーションと信頼関係が生まれていきます。
⑤ 院長に問いたい6つの“仕事設計”チェックリスト
□各職種ごとに「成果」と「役割」が明文化されているか?
□スタッフ個々に果たして欲しい役割は伝えられているか?
□成長のステップ(教育・キャリア)が見えるか?
□スタッフ同士の連携フローが明文化されているか?
□院長がいなくても判断できる仕組みがあるか?
□新人が「ここで成長できる」と思える仕事デザインになっているか?
まとめ
人手不足の時代に必要なのは、“人を集める力”ではなく“人を活かす構造”です。
求人広告の前に、まず院内の仕事設計を見直す。
それが、真の採用力・定着力を生み出す第一歩になります。
「採用できない」のではなく、「スタッフが遣り甲斐を感じる為の設計が足りない」。
この視点を持てるかどうかが、これからの医院経営の分かれ道です。
次回は第2回
「診療時間を延ばす=売上アップ」という誤解で、「量の経営」から「密度の経営」への転換について掘り下げます。
 |
|
 |
|
 |