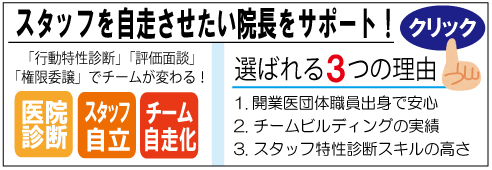多くの院長が「患者満足度」を重視しています。
アンケートを取って、★の数を気にして、クレームゼロを目指す。
一見、正しい経営のように見えますが、私はこう感じています。
「満足」は“結果”であり、「理解」は“関係の始まり”である。
つまり、「満足度」を追う医院は“評価される医院”にはなりますが、「理解度」を高める医院は“信頼される医院”になります。
そして、信頼される医院こそが、LTV(生涯来院価値)の高い患者を育てるのです。
① 満足は“過去の評価”、理解は“未来の関係”
満足度は、患者が治療を受けた直後の印象評価です。
「丁寧だった」「痛くなかった」「待ち時間が短かった」など、その瞬間の体験を数値化したものにすぎません。
一方、「理解度」は、患者が治療の意味をどれだけ腑に落としているかを示します。
たとえば、
・自分の病状と原因を理解している
・治療方針と目的を納得して選んでいる
・生活習慣がどのように影響しているかを知っている
この“理解”が深い患者ほど、治療を中断せず、予約キャンセルもせずに重症化予防にも通い続ける。
満足は“短期の評価”ですが、理解は“長期の信頼”を育てるのです。
② 満足度調査の落とし穴 ―「表面上の好印象」に惑わされる
患者アンケートで「とても満足」が並んでいる医院でも、定期来院率や紹介率が低いケースを見ます。
これは「好印象≠信頼」だからです。
行動経済学でいうと、これはピーク・エンドの法則(人は“最も印象的な瞬間と最後の瞬間”で全体を判断する)に支配されています。
つまり、
・最後の会計がスムーズだった
・スタッフの笑顔がよかった
という“表面の好印象”で高評価を得ても、患者の行動(再来・紹介・予防継続)は変わらないのです。
一方、信頼関係を築けた患者は院長にとって耳の痛いことも言ってくれる。医院にもっと良くなって欲しいと期待しているからです。
③ 患者理解度を高める3つの設計ポイント
“理解”を深めるには、「伝える」ではなく「共に考える」コミュニケーションが必要です。
⑴ 双方向の説明デザイン
一方的に説明するのではなく、
「この治療の目的の説明を聞いてどう感じますか?」
「今の状態について、気になることはありますか?」「どういう状態になることが理想ですか?」と問いを入れる。
人は“自分の言葉で考えた内容”しか記憶に残しません。そして自分で決めたと感じることで納得できるのです。
⑵ 期待値を正しく設定する
心理学では「期待値理論」があります。
期待が高すぎると、少しの不一致で不満が生まれる。
期待が現実と一致すると、満足が安定する。
だから、最初に「できること・できないこと」を明確にし、“正しい期待”を持ってもらうことが信頼構築につながります。
ホームページでもキラキラした内容で作れば新患獲得に繋がるのは事実ですが、期待値が上がった患者が来院してガッカリすることが無いようにする必要があります。
⑶ チームで「患者の理解」を確認する
・ドクターが治療方針説明
・歯科衛生士が補足・患者の質問を受け止める
・受付(診療スタッフ)が次回予約時に患者の理解度を再確認
この“三段階設計”ができている医院は、患者が安心して継続来院に繋がります。
④ 「信頼関係」を測る3つのKPI
“患者理解度”はアンケートでは測れませんが、次の3つの数値で見える化することが可能です。
|
指標 |
意味 |
改善アプローチ |
|
① 治療中断率 |
理解度が低いほど中断率が上がる |
「治療の目的」と「自分の役割」を再説明 |
|
② 定期来院率 |
医院への信頼のバロメーター |
来院目的を“予防・維持”に再定義 |
|
③ 紹介患者率 |
共感度・納得度の結果 |
患者の声を院内にフィードバックする仕組み |
⑤ 院長への問い:あなたの医院は「評価」か「信頼」か?
1.治療説明が“同意”ではなく“納得”に至っているか?
2.スタッフが「患者がどこまで理解したか」を把握しているか?
3.定期来院率を“満足度”よりも重要指標にしているか?
4.“説明の上手さ”より“共感を引き出す質問力”を育てているか?
5.アンケート結果を“改善の方向性”として活かせているか?
まとめ
患者満足度は「点」で測れる。
しかし、患者理解度は「線」で築かれる。
その線が太く、長く続くほど、医院の信頼と安定収益が積み上がっていきます。
“理解を育てる医院”は、治療を終えたあとも患者に選ばれる。
数値では測れない信頼こそ、医院の最大の資産なのです。
次回は第5回:
「“成功医院”の真似をやめよう ― 自院の“正解”を設計する」
流行を追う経営から、理念と地域に根ざした独自モデルへ。
「どこにもない医院」をどう創るかをお伝えします。
 |
|
 |
|
 |