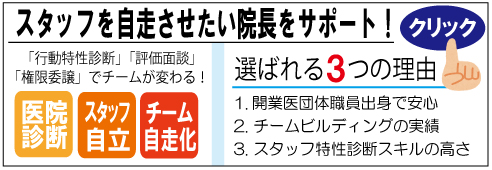歯科医院の院長は“人が動きたくなる仕組み”を理解できているか?
歯科医院の経営も、もはや「院長が法律」という時代ではありませんし、そういうやり方ではスタッフの自主性は育ちません。上場企業では組織管理や経営目標管理、働き甲斐を持てる環境の構築など幅広く取り組んでいますが、歯科医院も組織マネジメントを効果的にしてチームとして機能させる必要性が出てきました。 人材不足と価値観の変化が進む中、指示や命令だけでスタッフを動かす経営では、医院は成長の途中で頭打ちになり、発展も停滞します。
◆ スタッフは何で動くのか?
衛生要因(給与や条件)で人を動かすのには限界があります。 また、院長の「人間力」だけに頼る医院も組織の永続性を持ちません。
人に関する研究は心理学や脳科学で進められ、それらを学ぶことで傾向は見えてきていますが、 大切なのは「そのスタッフを肯定的に理解すること」に尽きます。
◆ “動きたくなる仕組み”をつくる視点
- ・スタッフ個々の特性を理解し、価値観ややりたいことを聞く
- ・そのスタッフが描く成長イメージに近づける様に一緒に小さな目標設定をする
- ・小さな目標を繰り返し達成してもらい自信をつけてもらう
- ・自己効力感が低いスタッフは「集団的効力感」に巻き込む
- ・現状維持バイアスを踏まえ、初期段階では指示+話し合いを並行して活用
- ・ティーチング → コーチング → 権限委譲 というステップを踏む
理念に基づき、スタッフ自身がプランを考え、発表し、周囲の賛同を得て実行する。 そして成果に繋げる経験を重ねることで、組織は自走型に変化します。 院長が日常診療を通じて「このスタッフは何に興味を持ち、どんな価値観を大切にしているか」を観察し、 そのスタッフの“ホットポイント”を見極めて関わることが、動機づけの出発点になるのです。
コーチング段階に入った場合には「指示量を減らす」必要がありますので「質問の使い方」を工夫してくださいね。
間違っても「答えを与える」「指示で修正させる」はやってはいけません。院長がスタッフの「考え失敗しながらも自分の力で正解に辿りつく、成果に繋げる」という成長の機会を奪っていては、いつまで経っても自走する組織には近づかないのです。
◆ まとめ
スタッフが「動きたくなる仕組み」とは、心理学や脳科学の理論だけで完結するものではありませんし、それらを使って人を動かそうという考え方は間違いです。 それらを学びスタッフを理解することに使う事が大切なのです。院長がスタッフ個々の特性に寄り添い、成長を後押しする環境を整えること。 それが、これからの歯科医院経営で求められる本質です。
国がこれから保険医療機関に求めてくるのは本質的であり、組織の成長度が低ければクリアできない課題です。今まではプロセス評価であり施設基準を取得して実行できていれば加算を取れた。しかし国は時間をかけながらもアウトカム評価を取り入れようとしていますので、治療において成果を出せる歯科医院が段階的に優遇されていくのです。
治療において成果を出す為にはスタッフの成長が欠かせない。
その為には先生の医院のメンバーに合った組織マネジメントの方法を見つけ出す必要があるのです。
先生の医院では、スタッフが「自分から動きたくなる仕組み」をどれだけ整えられていますか?