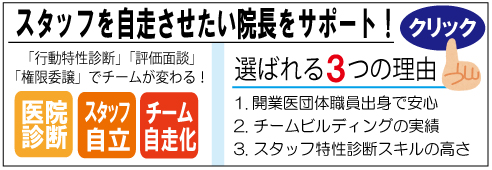お盆期間中、私は過去20年以上分の医療政策資料や診療報酬改定データを読み返し、2040年までの医療改革の方向性を改めて分析しました。その過程で「医療政策分析」及び「診療報酬改定予測」に特化して私が精度を高めてきたGPTsも活躍し、改めてGPTsに与える知識の質、プロンプト設計と質問の質の重要性を実感しました。
ただ、重要な医療計画の資料は生成AIで情報を集めたり要約しないで自分の目で資料を読んで分析しないと「政策の意図」は読み取れない。例えば資料の文言に「〇〇等」の「等」がついている事が重要な意味を持っていることもあるのです。
私と生成AIでは何にフォーカスして資料を分析するのかの基準が違いますので、AIに頼り切らずにツールとして使うことが大切だと思いました。
あと「確証バイアス」を防ぐ為にあえて自分の見立てへの否定的な意見を生成AIに求めることも重要だと思います。
分析できたとは言ってもあくまでも予測なので詳細な内容はブログでは公開できませんが、せっかくなので今日は2040年までの改革の大枠について私の見立てを書いていきますね。
政治における力関係が変化すれば政策も変わりますので、現時点ではそういう見方もあるんだな、という程度でお読み頂ければと思います。
医療DXがもたらす「可視化」と「評価」
医療DXは段階的に医療機関の
・請求情報
・診療情報
・経営情報
を統合・可視化します。その目的は重複診療の防止だけでなく、各医療機関の治療品質と経営の成果を定量的に把握し評価することです。つまり、診療の中身や結果が数値で比較され評価される時代が待ち受けているのです。
定量的に医療機関が丸裸にされていく。本格的な実態把握は標準的電子カルテが普及した以降になりますが、それ以前でも医療機関が報告しなければいけない情報は増えていくと思います。
今まで見えなかった部分が可視化されますので、エビデンスや算定ルールに沿った診療をしないと厳しいだろうなと感じます。
医療提供のパラダイムシフト
医療政策は長期的には「療養の提供」から「療養の提供+疾病の発生リスク管理・予防」へ移行します。国民一人ひとりの健康データ(PHR)が蓄積・共有され、健保組合を中心に健康ポイント等で評価される仕組みが進むでしょう。
2025年からはその“移行期”にあたります。将来的には国民も健康である為の取組み(健診受診や運動等)をどれ位しているのかでランク分けされる可能性もあるのです。
変化は“慢性疾患”のように進む
来年の診療報酬改定も、ミクロ視点では大きな変化は見えにくいかもしれません。しかし、2040年を見据えた評価項目が加われば、古い治療手法や評価基準は段階的に廃止されます。施設基準の要件も変わるでしょう。
だから「〇〇が〇点増えた、減った」という視点ではなく、国の医療政策を流れで視て、今後を予測しながら経営戦略を立てて医院経営を変化させることが大切なのです。
昔に「か強診」が出来た時に素直に施設基準を取得して算定できる様にした院長と、対応しなかった院長で経営面で大きな差となった様に、ジワジワと進む変化に対応していける医院だけが生き残っていけるのです。
国の改革は慢性疾患の進行のように静かに進みます。
いまや診療報酬改定は2040年に向けた医療政策を実現していく為のツールとなっているのです。
だから、大局的に2040年までの医療制度改革を予測することが出来ている院長は国の戦術の意味が理解できますし改定の半歩前に対応する準備も出来る。しかし、近視眼的に点数だけを見ている院長は今後の医療政策の流れが理解できていないので改定内容に振り回されるのです。
院長に求められる覚悟
改革の波に先手で対応するか、変化を軽視して受け身で臨むかで、2040年の医院の姿は全く違うものになります。
私としては、このブログを通じて一人でも多くの院長が危機感を持ち、改革への一歩を踏み出すきっかけになることを願っています。
結論:
2040年に向けた医療改革は「ある日突然」やってくるのではなく、2000年から計画的に始まっています。
改革の理由は医療費抑制だけではく、変化している医療需要や地域環境に医療機関が対応する様に国が促していることでもある。
あくまでも私が予測する2040年の到達イメージですが、、
2040年に向かう早期の段階で”包括評価+アウトカム評価”が完成され、AIレセプト審査が実施され、自動的、定量的に把握した医療機関の経営実態に合わせて診療報酬が調整されている。そして2040年には歯科医院の数は大幅に減少しており、都市部では大型化した歯科医院が増えています。う蝕マーケットの需要を支えてきた団塊の世代の多くはマーケットから退出し、2040年の時点で地域マーケットに55歳以上の人口が少ない場合にはう蝕治療型の歯科医院は苦戦しているでしょう。
そして国民は保険適用されない疾病のリスクに備える為に民間保険も活用している。自分のPHR(パーソナルヘルスレコード)を最適化させる為に健診を受け運動習慣を身につけようとしているのです。
もしかしたらヘルスケアウォッチが国民に配布されバイタルデータの分析結果がPHRとEHR(電子健康記録)に共有されているかもしれませんね。
良好なPHR情報を保険会社に提示することで民間保険の保険料の割引がされている。その為の準備も保険会社で進んでいます。
最終的には国は包括化された公的保険の上に民間保険を乗せた二重構造にしようとしていると私は考えています。行政機能や社会保障制度を民間に開放しろという海外からの圧力は昔からありますので、その流れが50年近くをかけて進められているのです。高額療養費制度の見直しもその流れの一つだと私は考えています。
2040年頃には医療機関は当たり前にEHRを活用して診療をする様になっているはずです。もちろん、医院のEMR(電子カルテ)情報も多職種に共有されているのです。
団塊の世代の需要で拡大している医療介護マーケットも2042年以降は縮小し始めますので、国は将来のマーケットの変化を見据えて政策を進めているのです。
だから医療機関が変化しないで生き残っていけるはずもない。
2040年に向けた院長としての覚悟と行動は、今この瞬間から問われているのです。
開業されている地域の状況を踏まえた経営戦略の立案でお困りならご相談ください。段階的にどういった経営対策を打つ必要があるのかを分析させて頂きます。
 |
|
 |
|
 |