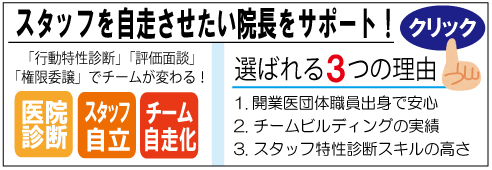今日は「変化に強いチームを育てる院長学 第三回」
「判断力を磨く “迷わない院長”の思考法 ~不確実な時代に何を基準に決めるのか」です。
近年、医療制度や経営環境の変化スピードが加速しています。
施設基準取得、デジタル化、地域包括ケア参加、口腔機能管理・矯正、働き方改革・・・
どれも院長が取組むべきかの“判断”を迫られるテーマです。
しかし、多くの院長がこう感じていませんか?
「経営的にどの方向に進むのが正しいのか分からない」
「決断した後、いつも迷いが残る」
実はそれ、経営者としての能力不足ではありません。
変化の時代には “正解”が存在しない のです。
求められているのは、「正解を探す力」ではなく「判断軸を持つ力」 です。
判断軸がないと「歯科界のトレンド」という訳の分からない言葉に惑わされてしまうのです。
① 判断を迷わせる2つのバイアス
人は誰でも無意識のうちに「思考の癖」を持っています。
特に院長が経営判断を誤りやすくする2つの心理バイアスがあります。
(1)過去依存バイアス(成功体験の呪縛)
「これまで上手くいったから、今回も大丈夫」
→ 医院のフェーズや社会環境が変わっても、同じ戦略を続けてしまう。
例:
・過去に成功した広告媒体を費用対効果が悪くなっても延々と使い続ける。
・新しい採用チャネルの採用やDX投資を避ける。
結果、変化への対応が遅れ、医院が硬直化していきます。
(2)感情依存バイアス(安心の錯覚)
「なんとなく不安だから、今はやめておこう」
→ 理屈より感情を優先して判断を先送りしてしまう。
例:
・新しい施設基準などへの対応を“現場が混乱するかも”と先延ばしにする。
・スタッフの提案に“うちでは無理”と返してチャンスを逃す。
いずれも、「変化の痛み」を避けようとする心の働きです。
② “正解を求めない”ことが判断力を高める
不確実(VUCA・ブーカ)な時代において、判断の目的は「正解を出すこと」ではありません。
目的は、“意味のある選択”をし続けること。
経営判断における“意味”とは、医院の 理念・ビジョン・方向性に一貫しているかどうか です。
もし「理念に照らして正しい」と言えるなら、
それがたとえ結果として失敗に見えても、組織は学びに変えられます。
逆に、理念と関係のない“数値優先の判断”を繰り返すと、短期的な成果が出てもチームの信頼は失われます。
判断に迷った時こそ
「この選択は、理念とつながっているか?」という問いを自分に投げかけてください。
スタッフが理念行動を出来ていないのなら、それは院長の判断軸がブレている可能性が高いからです。
③ “考える院長”が実践している3つの思考習慣
判断力を磨くには、「考える力」を鍛えるしかありません。
有能な経営者やリーダーが共通して持っている3つの思考習慣があります。
(1)データで冷静に現実を見る
感情ではなく、ファクト(事実)に立ち返る。
キャンセル率・離職率・LTV・生産性
数字を「評価」ではなく「観察装置」として使う。
数字は“チームメンバーを責める材料”ではなく、“考える材料”です。
(2)未来を先取りして仮説を立てる
変化を待つのではなく、先に小さく試す。
たとえば新しいチーム運営制度を“1ユニットだけ試行”してから全体展開する。
これが「OODAループ」(観察→方向付け→決定→行動)の考え方です。
(3)多様な視点を取り入れる
院長一人で判断を抱え込むと、視野が狭くなります。
有能なリーダーほど、“対話による思考” を重視します。
・スタッフや副院長と対話する
・外部コンサルタントと仮説をぶつけ合う
・数値だけでなく「現場の声」も判断材料にする
他者の視点を借りることは、迷いを消すことではなく“精度を上げる”ことです。
④ 「考える院長」が育てるチームは強い
院長が考えることをやめた医院では、スタッフも思考を止めます。
逆に、“考える院長”の姿勢 はチーム全体に伝染します。
・現場で起こる課題を「考えて解決する」文化が育つ
・スタッフが“答えを聞く”のではなく“提案する”ようになる
・チームが自立し、変化に対応できる組織へ
“迷わない院長”とは、考えない院長ではなく、考え続ける院長です。
⑤ 院長への3つの問い
(1)最近「変化を避けた判断」をしませんでしたか?
(2) 先生の決断は、理念とつながっていますか?ブレていませんか?
(3)チームに「考える文化」を育てていますか?
私がチーム作りのサポートを始めた初期には、院長の判断軸がブレている医院では「院長は結局何がやりたいのですか?」とスタッフが私に聞いてきます。
スタッフには新たな仕組みの導入が理念実現に繋がっているという実感がなく、負担感ばかりが増していくのです。
まとめ
不確実な時代に強いのは、「正しい院長」ではなく、「考え続ける院長」、そして「ブレない院長」です。
判断力とは、経験や直感の積み重ねではなく、理念に基づき“考える習慣”を持ち、行動に繋げること です。
迷うことを恐れず、“理念に基づいた意味のある判断”を積み重ねる院長が、未来を切り拓いていくのです。
次回予告:
第4回「人を育てる院長、人に依存する院長」
教育の本質は“任せる勇気”にある。
“任せる仕組み”がある医院と、院長が抱え込む医院の違いを紐解きます。
 |
|
 |
|
 |