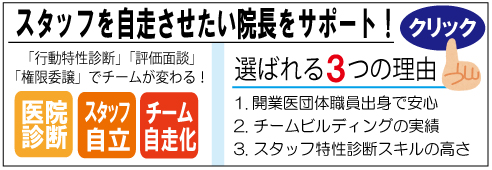はじめに:スタッフ育成に“ストレス”は必要か?
「スタッフにあれもこれも頼みすぎてないだろうか…」
「負担をかけすぎて辞められたらどうしよう…」
そんな不安を感じて、医院の取り組みをセーブしてしまう院長先生も多いのではないでしょうか。
ですが、変化のない職場で人は育つでしょうか?
人間の脳は本能的に「変化=ストレス」を嫌う傾向があります。
しかし、それを理由に変化から逃げていては、歯科医院としての進化も止まってしまうのです。
ストレスは“敵”ではない――脳科学が示す「成長の鍵」
脳科学によると、人は適度なストレス(チャレンジ)を経験することで脳の可塑性が高まり、成長しやすくなることが分かっています。
・新しい業務への挑戦
・診療外の勉強会やディスカッション
・院内の課題解決プロジェクト
・患者対応の質を高める工夫
こうした変化に触れることで、脳の「海馬」が刺激され、神経細胞の新生が起こります。
つまり、スタッフが成長するには「変化(=成長ストレス)」が必要不可欠なのです。
ただし、無理は禁物。「無茶ぶり」が逆効果になる理由
とはいえ、負荷が大きすぎるストレスは逆効果です。
スタッフが「どうせ無理」「自分にはできない」と感じてしまうと、脳はシャットダウンし、成長モードには入りません(逃走反応)。
ここでカギになるのが、ストレスを「チャレンジ反応」へ導く設計です。
・「やればできそう」と思える小さな目標設定
・伴走するメンター・幹部の存在
・失敗してもフォローされるという安心感
・成功した時の承認とスキル評価の仕組み
これらを組み合わせることで、スタッフの自己効力感(自信)を育みながら成長ストレスを乗り越えさせることができます。
成長度別に負荷を変える。それが“無茶ぶり”との境界線
すべてのスタッフに同じ負荷をかけてしまうと、当然無理が生じます。
重要なのは、個々の成長フェーズに応じて任せるレベルを調整することです。
・新人スタッフ:ルールやマニュアルベースの小さな改善提案
・中堅スタッフ:患者満足度を上げる仕組み改善の担当
・リーダー候補:医院の新プロジェクトの企画運営
特に成長意欲の高いスタッフには、ある種の“無茶ぶり”が大きな成長機会となることもあります。
先生の医院では、スタッフ一人ひとりの成長段階に合わせたチャレンジ機会を、設計できていますか?
終わりに:小さな反発の先に、組織の変化はある
新しいことに取り組むと、「なんで私が?」「今じゃなくても…」「人手が足りない」といった反発が起こることもあります。
でも、それは変化に対する脳の自然な反応にすぎません。
スタッフの反発があったから諦めるのではなく、そこからどう進めるのかが大切なのです。
重要なのは、プロジェクトの重要性の理解や、チャレンジのその先にある「乗り越えた達成感」や「新たなスキルの獲得」を経験させることです。
それが、スタッフ自身の“やりがい”につながり、医院全体の進化にもつながっていきます。
「チャレンジ反応」が起きる適度な成長ストレスを、どのようにデザインできるか?
これは、院長が「人を育てる経営者」として向き合うべき大きなテーマです。
先生の医院では、スタッフに“成長ストレス”を与えられていますか?
もし今、「挑戦のない日々」に組織が停滞しているなら――
それは、“やさしさ”ではなく“可能性の損失”かもしれません。
スタッフ育成のための“チャレンジ設計”に興味がある先生はご相談くださいね。
 |
|
 |
|
 |