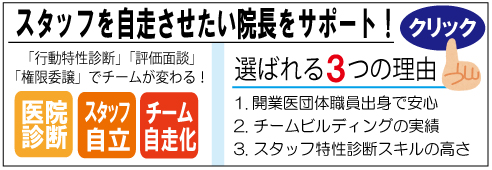歯科医療は従来の「治療中心型」から、「管理・予防・連携型」へ大きく舵を切り始めています。
軽度のう蝕や安定期の歯周病、口腔機能の維持、さらには生活習慣病まで。
これからは医科や多職種と連携しながら、疾患の悪化を防ぎ、患者の生活全体をサポートすることが求められるのです。
真の“かかりつけ歯科医院”とは、患者本人だけでなく家族単位で診療を行い、世代を超えて通い続けてもらえる医院のことを指します。
実際にかかりつけ患者が多い医院では「家族ぐるみ」での来院が多く、それが患者からの信頼の証なのです。
患者との心理的距離が広がる危険性
しかし近年、歯科医院では「生産性」や「接客の型」を重視するあまり、患者の心理面や背景を把握できないまま治療を進めるケースが増えています。
その結果、診療空間は必要最低限の会話だけで終わり、患者が心を開かないまま治療が進むことも少なくありません。
これは単なる接遇の問題ではなく、院長の医院づくりの姿勢に直結しています。
時間配分が“かかりつけ化”を左右する
例えば、予定していた10分の診療時間が8分に短縮された場合。
患者目線のスタッフは大切な説明や関係構築の時間を守りつつ、他を効率化して時間内に収めます。
一方で、作業に時間を割きすぎるスタッフは、重要な会話や患者理解の時間を削ってしまうのです。
この違いが次のような数値に表れます:
・キャンセル率
・治療・施術の中断率
・紹介患者数
・SPTへの移行率
・1年後の継続来院率
「かかりつけ患者」を増やすことが生存戦略になる
かつては、治療が終われば患者が来院しなくなるのが当たり前でした。
しかし今後は、「再診」「管理料」を通じて、患者を継続的にサポートできるかどうかが評価されます。
診療報酬体系もアウトカム評価へ移行し始めており、“5年以上通い続けるかかりつけ患者”の存在が経営の安定を決定づける時代に入っています。
先生の医院では、5年以上通い続けている患者はどれくらいいますか?
出来高払いが徐々に姿を消していく今後の時代、かかりつけ患者を増やすことができなければ、保険診療だけでの経営はますます難しくなるでしょう。
 |
|
 |
|
 |