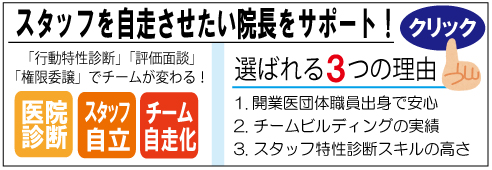今日は「数字の裏側にある“経営の真実”」シリーズ第2回です。
経営セミナーやコンサルティングの現場で、よく使われる指標の一つが「スタッフ一人あたり売上(生産性)」です。
計算式はシンプルです。
スタッフ一人あたり売上=総売上 ÷ スタッフ数
この指標は一見わかりやすく、“生産性の高さ”を測るのに便利に思えます。
しかし、この数字をそのまま目標にしてはいけません。
経営においては必要不可欠なのですが、この指標には「人を数字で追い込む危険性」と、「組織のバランスを壊す構造的欠陥」があるからです。
今日は、数字の裏に隠れた“経営の真実”を一緒に考えていきましょう。
① 「スタッフ一人あたり売上」が示すものと示さないもの
この指標が便利なのは、「業績のざっくり比較」ができる点です。
同規模の医院と比べて効率が良いのか悪いのか、前年と比べて生産性が向上しているのかがすぐに見えます。
しかし、そこに落とし穴があります。
「数字」は“結果”であり、“原因”ではない。
たとえば、スタッフ一人あたり売上が低い医院でも、
・予防中心で時間をかけて説明している
・高齢者や在宅診療が多く単価が低い
・新人スタッフを教育中で時間効率が下がっている
という理由があるかもしれません。
つまり、この数字だけでは理念実現において何が良くて、何が課題かが見えないのです。
確かに、生産性は無視して治療品質だけを追いかけると経営的には厳しくなります。
生産性を基準にすれば収益性は確かに向上するのですが、スタッフの心の中で失うものもあるのです。
② 「数字で追う」ことで起こる3つの弊害
(1) チームの連帯感が失われる
「誰がどれだけ売上を上げたか」が可視化されると自然と競争意識が生まれます。
表面的には頑張っているように見えても、“協働”ではなく“個人主義”が強まる。
結果として、医院全体の一体感が失われます。
(2)数字に表れない貢献が軽視される
例えば、
・患者対応でクレームを防いだ受付
・新人教育を地道に支えている中堅スタッフ
・チーム全体の雰囲気を良くしてくれている人
こうした貢献は「売上」には反映されません。
360度評価を取り入れている歯科医院も増えていますが、360度評価も主観的評価の領域を抜け出ることは出来ないのです。
しかし、医院経営の“基盤”はむしろこの集団維持活動にあります。
「見えない貢献を軽視した組織」は、必ず長期的に崩れるのです。
(3)現場が“効率”に偏り“価値”を見失う
「数字を上げなければ」と意識すると、治療やケアの時間短縮や単価アップに意識が偏ります。
結果として、
・患者への説明が簡略化される(治療への理解度が下る)
・コミュニケーションが減る
・患者の困ったより効率が優先されやすくなる
・スタッフが疲弊する
そんな悪循環が起こりやすくなるのです。
③ 「生産性」を人ではなく“仕組み”で見る
本来、経営者が見るべきは“人の数字”ではなく、“仕組みの数字”です。
たとえば
・1ユニットあたり売上(仕組みの生産性と治療説明品質)
・1来院あたり単価(治療計画と説明品質)
・予約稼働率(治療希望患者の予約確定)
これらは環境設計とオペレーションの質を示します。
つまり、
「人が悪い」のではなく、「仕組みが未整備」なのです。
医院が成長し続けるためには、「個人の頑張り」ではなく「全体の設計」を改善しなければなりません。
④ スタッフ一人あたり売上を“人の成長指標”に変える方法
数字を追うこと自体が悪いわけではありません。
理念の実現に近づいているのかも定量的に測定しなければ自己満足で終わるからです。
重要なのは、“数字の意味づけ”を変えることです。
(1)「目標」ではなく「振り返りの指標」にする
「今月は○○万円を目指そう」ではなく、
「今月はこの取り組みで、結果的にどう数字が動いたか。それによって患者にどう貢献できたのか」
「何をどう改善すれば診療品質と治療単価のアップに繋がるか。治療単価のアップによって患者が得られる利益は何か」という“プロセス分析”に使う。
数字を“結果の評価”ではなく“学び”に転換することが重要です。
数字を重視する多くの医院で「手段の目的化」が発生してスタッフが疲弊している。
目的を追うのではなく数字(手段)を追いかける日常に未来が見えなくなっているのです。
(2)“成果”ではなく“成長”を評価する
売上よりも、「患者理解度」「説明力」「再来率」など、価値を生み出す行動を評価項目に加える。
例えば、SPT移行率は初診カウンセリング、歯周病検査、歯周病コンサル、OHIなどの品質を評価したものですが、同時に売上にも繋がります。
そしてスタッフが「数字の裏にある価値(患者を離脱させずに健康を守る)」を実感できるようになります。
数字の達成によってどんな価値が達成されるのかが見えることで、数字を追うことの意味が見えやすくなるのです。
(3) チームで「数字を共有」し、「原因を話し合う」
院長だけが数字を見るのではなく、ミーティングで共有し、
「なぜこの数字になったのか?」
「何を変えれば良くなるか?」
をチームで話す。
これにより、数字が“責めるための道具”ではなく、“治療品質の改善の言葉”に変わります。
⑤ 院長への問い:あなたの数字の使い方は?
1.「売上」でスタッフを評価していないか?
2.「仕組みの問題」を「人の問題」にしていないか?
3.「数字=目的」になっていないか?
4.「数字を通して学ぶ文化」があるか?
5.「数字の背景にある努力」を見ようとしているか?
まとめ
「スタッフ一人あたり売上(生産性)」は、組織の健康状態を測る“体温計”のようなものです。
高ければ良い、低ければ悪いではなく、その“温度変化の理由”を読み解くことが大切です。
数字は「人を責めるため」ではなく、「組織を成長させるため」にある。
数字に追われる医院は壊れ、数字を“使いこなす医院”が育つ。
経営とは、数字ではなく“人と仕組み”を設計することなのです。
次回は第3回:
「KPIが機能しないのは“数字を追っている”からではなく、“意味を見失っている”から」をお届けします。
目標管理の形骸化を防ぎ、“数字に魂を入れる”方法を解説します。
 |
|
 |
|
 |