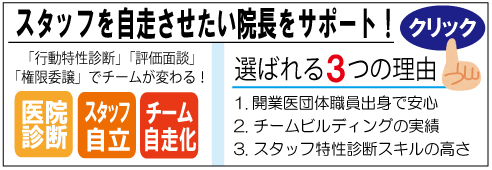はじめに:国の医療政策が歯科医院に突きつける“問い”
近年、診療報酬改定やDX推進といった制度の変化を前に、「この先、歯科医院はどう対応していけば良いのか?」と悩む院長が増えています。
その背景には、「地域包括ケアシステム」という国の医療ビジョンの本格運用があります。
いまや診療報酬は「治療」だけでなく、「重症化予防」「口腔管理」「医科・歯科・多職種連携」など、地域における歯科の役割を果たす医院に配分される設計になっています。
それでも、未だ多くの歯科医院がその流れに乗りきれていないのが現状です。
では、今後どのような姿勢と準備が求められるのでしょうか?
地域包括ケアに向けた国の方針はブレていない
厚労省が掲げる「地域包括ケアシステム」は、住み慣れた地域で医療・介護・生活支援が完結する体制を目指すもので、そこにおける歯科医療の役割は明確です。
・かかりつけ歯科医としての重症化予防・管理・生活支援機能
・訪問診療・口腔衛生管理による全身疾患リスクの低減
・医科、介護、薬局、ケアマネ、医療専門職などとの多職種連携による包括的支援
こうした流れを受け、「か強診」は「口腔管理体制強化加算(口管強基準)」に進化しています。これは単なるネーミング変更ではなく、“歯科医院の社会的役割”をさらに問うメッセージなのです。
令和8年の歯科診療報酬改定も上記の方針を実現する為におこなわれます。
今後の改定ではアウトカム評価が強化されます。つまり、全国の歯科医院が国が求める成果を出せなければ点数配分がされなくなるのです。令和6年の診療報酬改定で点数がついたものも成果検証で結果を出せていなければ評価方法が変更になったり減点、廃止となることもあるのです。
先に介護の世界に「科学的介護」が持ち込まれ、一定の検証をした上で医療にも適用しようとしていると私は捉えています。
医療制度改革はまだ始まったばかり、これからは2040年に向けて第二弾の改革が進むのです。
医療DXがその改革の中心を担うと私は考えています。
なぜ歯科医院の“無関心”が、診療報酬を下げてしまうのか?
現在、口管強基準を取得している歯科医院は全国でも限られています。
訪問診療に取り組む医院や、医科との連携加算を算定している医院もごくわずか。
したがって、それらの加算点数も算定していない。
このような現実に対して、財務省は「歯科医院は利益が出ている」と判断し、本体マイナス改定を正当化しようとしています。
つまり、多くの歯科医院が評価される基準を取っていない=診療報酬を上げる必要性がないという論理が成立してしまうのです。
もしこのまま多くの院長が無関心でいれば、「評価の芽」を自ら摘むことになりかねません。
2019年以降、国は歯科医療を重視し様々な施策を実施し診療報酬上の評価もしてきたのに、歯科界がそのチャンスを掴まないでいるのです。
地域包括ケアは「訪問診療」だけが入口ではない
「うちは訪問診療は難しいから、地域包括ケアは関係ない」
そう考える院長も多いかもしれません。
しかし、訪問をしていなくても、地域包括ケアに参画する方法はあります。
・院内で生活習慣や全身疾患への配慮を伝える口腔管理の仕組み
・生活習慣病を持つ患者、障害をもつ患者に関する医科や多職種との連携
・介護施設や地域包括支援センターとの情報共有
・歯科衛生士による予防介入とその記録・報告
・口腔機能管理やSPT加算などを通じた継続的なケアと管理
これらの実践は、すでに「診療報酬」で評価されている項目でもあります。
連携を推進する為に「連携カルテ」を作成したり、独自でサマリーを作成して情報共有を進めるなど、国のDXによる情報共有の仕組みが機能する前にもやれることは多いのです。
院長の覚悟が、地域と歯科医療の未来を決める
令和8年の診療報酬改定では、「歯科医療その1」がこれから発出されます。
国は「バラ色の改定」はしません。しかし、「役割を果たしている医院には評価を与える」という姿勢は一貫しています。
だからこそ、
・施設基準をクリアすることに挑戦し
・記録・連携・フィードバックといった対応を強化し
・“地域で必要とされる歯科医院”として存在価値を示す
この取り組みが、経営の安定と地域の信頼の両方を手に入れる道となるのです。
おわりに:先生の医院は、地域にどう貢献していますか?
経営だけを考えれば、確かに他にも生き残る方法はあります。
しかし、「歯科医院が社会に必要とされ続ける」には、国の求める医療像に応えていく努力が不可欠です。
先生は地域包括ケアに本気で参入する覚悟はありますか?
令和8年の診療報酬改定を前に、いまこそ医院としてのスタンスを明確にする時です。
制度対応だけでなく、戦略的な施設基準の取得とチームづくりについて、一度経営相談してみませんか?