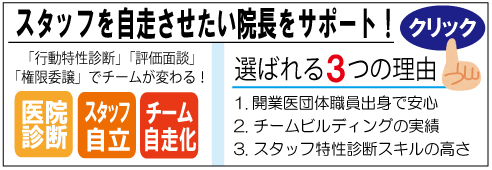はじめに:「集患できたのに定着しない…」はマーケティングの構造的な問題かもしれません
「Web広告やMEO対策で新患は来るようになった」
「でも治療中断率が低下しない。継続来院率が向上しない。歯科衛生士枠の予約が増えていかない」
「患者フォローがうまくいかない」
このような声を多くの院長から聞きます。
それは、“外部マーケティング”と“内部マーケティング”の連動ができていないサインかもしれません。
どれほど新患が集まっても、リピート、クロスセル・アップセル、継続来院患者、紹介が生まれなければ医院は成長しません。
今回は、「外部で集め、内部で育てる」マーケティングの仕組みづくりについて、実践的に解説していきます。
外部マーケティングの役割と限界
まず、歯科医院の外部マーケティングとは以下のようなものです。
・SEO、MEO対策、ホームページ運用
・GoogleマップのMEO対策
・Web広告(リスティング、SNS)
・ポータルサイト掲載
・地域広告(折込チラシ、看板)
これらは“認知拡大”と“新患の獲得”には非常に有効です。
しかし、ここで終わってしまうと、「主訴の治療で終わる患者」が大量に生まれる構造になります。
また、新患を集めても主訴のみ患者やダツリループ患者の比率が多ければ広告費に見合う収益の確保には繋がりません。
だからこそ、医院の成長に必要なのは“内部マーケティング”の設計と運用”です。
内部マーケティングの目的は「再来院と紹介を生むこと」
内部マーケティングとは、医院の中で患者に信頼と満足を感じてもらい、継続通院・紹介につなげる取り組みです。
・初診時の印象設計(受付・案内・診療導線)
・丁寧な説明とカウンセリングによる納得感
・歯科衛生士による治療、定期管理の価値伝達
・アフターフォローや再予約の声かけタイミング
・待ち時間や接遇、空間づくりを含めた“感情体験”
内部マーケティングは、患者の感情・体験・記憶に働きかけることが主目的です。
例えば、生産性を高める取り組みによって上記が犠牲になっていないかを注意して見ておく必要があります。
複数の穴が空いているバケツに水を注いでも水が溜まることはないからです。
先生の医院では、患者が「また来たい」「家族にも勧めたい」と感じる仕掛けが、医院全体で機能していますか?
「初診対応→カウンセリング→定期メンテナンス」までの流れを設計する
効果的な内部マーケティングには、「流れの設計」が不可欠です。
以下は、患者の体験ステージに沿った対応ポイントの例です。
1)初診時:医院の“印象”を決める接遇と導線
→受付・案内・診療スタッフの声かけルールを整備
→「安心」「清潔」「話しやすさ」の体験提供
2)カウンセリング:治療内容と価値の“納得”を引き出す
→治療コーディネーターやドクターが丁寧に説明、患者の話を聴くことを重視する
→患者のニーズに合わせた提案と選択肢の提示
3)定期管理:継続来院の“習慣化”を促す
歯周病は慢性疾患であり症状を安定させてからの重症化予防が重要だという事を患者に伝えます。
→歯科衛生士によるケアと管理、セルフケアの価値を伝える
→次回予約を必ず取り、来院理由を明確に伝える
この流れが仕組みとしてチーム全体に浸透していれば、リピート率は格段に上がります。
もう、リコール再初診をされている院長はいないとは思いますが、再来院率が低く患者の利益にならないリコール再初診ではなく、継続管理の必要性をきちんと患者に伝えて継続来院率を高めていく取組みが必要なのです。
口コミ・紹介を生む“感情設計”とは?
多くの紹介や高評価の口コミは、「診療技術」だけではなく「感情体験」から生まれます。
・「安心できた」「信頼できる」「スタッフが丁寧だった」
・「子どもが嫌がらずに通える」「説明がわかりやすかった」
これらはすべて、患者の“感情記憶”に残る接点が医院内にあるかどうかで決まります。
そのためには以下のような感情設計が有効です。
・初診時のヒアリングと目線を合わせた会話
・不安や不満を先読みした説明・フォロー
・笑顔・声のトーン・名前で呼ぶ対応の徹底
・スタッフ同士の雰囲気の良さが患者にも伝わる
感情設計は、“ちょっとした差”が大きな印象を生み出します。
私がクライアント歯科医院で感情設計に取り組んで半年後に「子どもの新患を月20人以上増やせた」のも、”感情”が動くことによって”口コミ”が生まれることを知っていたからです。
マーケティングは「院長だけ」ではなく「チームで回す仕組み」に
最後に重要なのは、マーケティングを“担当者任せ”にしないことです。
・受付・診療スタッフ・歯科衛生士・治療コーディネーター
それぞれが“どこで患者に価値を伝えるか”を理解し、日々実行することで、医院全体の体験価値が一貫します。
また、月次で以下のような数値管理を行うことで、PDCAを回しやすくなります。
・初診→2回目来院率
・治療計画完了率
・歯科衛生士のSPT枠継続率
・紹介による新患割合
・口コミ件数と内容分析
これにより、マーケティングは「感覚」ではなく「戦略」として医院に定着していきます。
おわりに:「集める」から「育てる」へ。仕組みとしてのマーケティング設計を
これからの歯科医院経営では、「集患」だけで満足していては成長が止まります。
・外部で“認知と新患獲得”
・内部で“満足・継続・紹介”
この2つがつながってこそ、医院のブランドと収益の持続性が生まれます。
先生の医院では、マーケティングが「一部の施策」にとどまっていないでしょうか?
それとも、「医院全体の仕組み」として機能しているでしょうか?
もし“外部だけ”に偏っていたり、“感覚で運用している”状況であれば、
今こそ内部マーケティングの設計と仕組み化に取り組む絶好のタイミングです。
内部マーケティングを強化したい、中断患者を減らしたいとお考えの院長はぜひご相談くださいね。