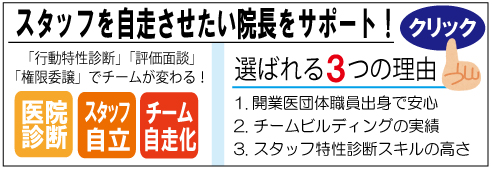歯科医院経営は、地元の人口動態に直結します。地域が不便になり働く場がなければ人々は生活の為に移動を始め、移動できない高齢者が残されるからです。
私は経営環境分析の際、地域を以下のように分類しています。
→ 増加期:高齢者を除く全年齢層の人口が増加
→ 微増期:年少人口は減少しているが、生産年齢人口1・2は増加
→ 減少期1:高齢者人口が増加。年少人口と生産年齢人口1は減少、生産年齢人口2は横ばいまたは微増
→ 減少期2:年少人口、生産年齢人口1・2が大幅減。高齢者人口が爆発的に増加
→ 減少末期:高齢者人口でさえも減少し始める
このように分類し、それぞれのステージに合わせた経営戦略を立案しています。
たとえば「減少期2」では、高齢者向け訪問歯科のニーズが高まりますが、同時に人材不足によりユニット稼働率が悪化するなどの課題に直面しやすくなります。
高齢者人口が増えても、次のような人材確保の壁があります。
→ 地元スタッフや勤務医・歯科衛生士が集まりにくい
→ 夕方以降の人手が足りず、予約枠を閉じることが頻発
→ 訪問専門の人材が不足し外来と兼任するようになり、高齢者ニーズに応えられない
→ ユニットが空き、固定費だけが増える
つまり、生産年齢人口が減少する地域では訪問需要はあるが応えられないという状況に陥りやすいのです。
特に地方の過疎地域では人材確保の難易度がさらに高まり、十分な需要があってもそれを掴めないという「成長の罠」に陥ることがあります。
→ ユニットを稼働枠いっぱいに使えず、夕方枠を閉じざるを得ない
→ 生産年齢人口が減少し、一般診療が滞る。補綴や自費の収益も減少
→ 女性や高齢者の労働参加率が上昇し、平日昼間の予約が埋まりにくい
院長がリタイア間近なら、規模を縮小しながら継続するという選択肢もありますが、30〜50代の院長にとっては、「縮小」だけでなく戦略的成長が不可欠です。
1.地域人口分類を可視化し、今後10年の人口推移を見通す
2.現在の人材供給力(スタッフ数・採用力)と地域シェア力を評価
3.自院の強みを踏まえ、地域連携・訪問歯科・重症化予防重点・審美/自費特化・複数医院化などの方向性を選択
4.採用力・育成力・収益モデルを一体で設計する(縮小強化、拡大強化、移転、専門化、訪問特化等)
5.ユニット稼働率、スタッフ稼働率、予約キャンセル率などの「地域適正指標」をKPIとして定期測定
現在の売上が院長の自費治療ブランドへの依存度が高ければ医院売却は困難です。
地域にどんなマーケットニーズがあり、人口動態や地域経済の変化によって今後どの様に変化していくのか?そしてマーケットは医院を継続発展させていけるだけのボリュームがあるのか?などを分析し、どんな戦略を立てるのかを決めるのです。これからの時代は「縮小強化」も選択肢の一つに入ってくると考えています。
はい。以下のように異なります。
◆ リタイア間近(55歳前後)
→ 経営規模の縮小+内部効率化→収益力アップ(ユニット削減、非常勤活用)で安定継続
→減少期1までで大都市部郊外、人口規模が20万人以上、かつ新規開業が複数ある地域であれば、収益力アップと最新歯科医療への対応で収益力を強化し事業承継や売却を目指す
◆ 若年院長(30〜40代前半)
→ 地域性に応じた差別化(高齢者/予防/自費)
→ 縮小ではなく「持続可能な成長」体制の構築。地域シェア率を高める
→ 採用・育成・収益率の壁を突破できる組織設計
→基幹都市への早期移転を検討する
→ 地域を人口推移で「段階的に分類」し、医院の将来リスクを見極めよう
→ 高齢者ニーズが高くても、人材不足で訪問体制が組めない「成長の罠」に注意
→ 若手院長は、市場に合わせた収益モデルと採用・育成戦略をセットで構築することが不可欠
大切なのは「継続的に分析し、早めに決断し、素早く動く」ということです。
地域は減少期2や減少末期で、買い物難民が出始めている。歯科医院の新規開業もなく地域の医院の多くは小規模で勢いがなく、院長の平均年齢も高い。そういう地域で院長の年齢が高いと打てる対策が限られますので、対策しても成果には繋がりにくいのです。
先生の医院は、将来の市場変化(少子高齢化・人口減少)をどう予測し、どの戦略で対応していますか?
私が提供している地域の経営環境分析は、とても実践的で役立つとご好評をいただいています。