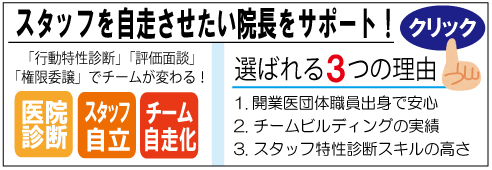受付対応が経営成果に与えるインパクトとは?
先生の医院では、受付スタッフの対応について定期的に振り返る機会を設けていますか?
歯科医院における受付対応は、単なる「受付業務」ではありません。患者さんにとって最初に接する“医院の顔”であり、その第一印象が通院の継続、自費治療の選択、さらには紹介や口コミに直結します。特に都市部や郊外の競争が激しいエリアでは、技術力や設備に加えて「感じの良さ」が来院の決め手になることも少なくありません。
ある郊外の中規模歯科医院では、受付スタッフ(診療スタッフも)の接遇改善に取り組んだことで、Google口コミの評価が★3.4から★4.1に向上。これにより月間の新患数が平均8人増加しました。これは単なる印象の話ではなく、確かな経営成果につながる「戦略的な仕組み化」の成功例といえるでしょう。
接遇のバラつきをなくす「受付スクリプト」とは?
接遇改善の第一歩は、「属人化の排除」です。どれだけ優秀なスタッフがいても、個人の経験や感覚だけに頼っていては、医院全体の対応力は安定しません。重要なのは、“誰が対応しても一定以上のクオリティが担保されること”。
そのためには、対応フローの見える化=「受付スクリプト」の整備が有効です。具体的には以下のような内容を明文化します。
・初診患者、再診患者への声かけや案内の順序(患者を満足させる虎の巻)
・患者が治療予約を取るときの具体的な応対方法
・患者の要望を聞いた時の治療チームとの具体的な連携方法(電話、治療前‣後)
・キャンセルや遅刻連絡時の対応パターン
・クレームへの一次対応のルールと二次対応マニュアル
・患者の体調悪化、交通事故患者など緊急時対応
このスクリプトを用いてロールプレイを定期的に実施することで、「知っているけれど、できていない」状況を減らすことができます。これは、心理学でいう“経験学習モデル(Kolb)”の「具体的体験」→「内省的観察」→「概念化」→「実践への応用」のサイクルを回すことにもつながります。学校教育でも使われているアクティブラーニングの仕組みがこれからの歯科医院には必要不可欠なのです。
定量評価とフィードバックで「受付の質」は高まる
受付対応の改善においては、「感覚」ではなく「数値」で変化を測る視点も大切です。たとえば以下のようなKPI(重要業績評価指標)を設定する医院もあります。
・新患カウンセリング後の自費選択率
・患者アンケートにおける受付満足度(★評価とコメント内容)
※プラス評価も意識的に拾う。受付スタッフが萎縮しないことが大切
・クレームや指摘件数の月次推移
・Google口コミの★数とコメント内容
これらをもとに、月1回のフィードバック面談を実施している医院では、スタッフが自らの役割を「業務」ではなく「患者体験の一部」として捉えるようになり、主体性とモチベーションが向上しています。
さらに、受付専任者と診療スタッフがお互いの業務を一定期間経験することで、部署間の相互理解が進み、離職率の低下にもつながっています。
チームの一員として受付が機能する組織設計を
受付が単なる「予約を取る人」から、「医院の理念を体現するチームメンバー」に変わるためには、院長の明確なメッセージと仕組みが必要です。
実際に成果を出している医院では、
・月1回のスタッフミーティングで受付対応の成功・失敗事例を共有
・受付スタッフが診療改善ミーティングに参加
・対応スキルに応じた評価制度(ステップアップ制度)を導入
といった取り組みが行われています。これにより、受付が「自分たちも診療品質に貢献している」という意識を持ち、チーム全体のエンゲージメントが高まります。
先生の医院では「受付対応の質」をどうマネジメントしていますか?
今後の診療報酬改定では、「かかりつけ機能」「継続管理」「チーム医療、連携」がますます重視されていく方向です。こうした中、受付対応の仕組み化は、単なる印象管理ではなく“医院の成長戦略”の一部といえるでしょう。
先生の医院では、受付対応の「見える化」や「仕組み化」に取り組んでいますか?
また、定期的な評価やフィードバックの仕組みは整備されていますか?
もっと詳しく知りたい、具体的なスクリプトや品質チェックシート等を作りたいとお考えでしたら、お気軽にご相談ください。先生の理念に合った運用方法をご提案いたします。