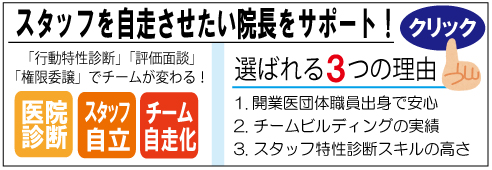財政制度審議会・中医協の資料、議事録の読み方講座
今後の歯科医院経営を考えるうえで、国の医療政策の動向を知ることは不可欠です。特に診療報酬改定に向けた財政制度審議会や中央社会保険医療協議会(中医協)、各部会、経済財政諮問会議等の議事録や資料は、貴重な「羅針盤」となり得ます。本記事では、こうした資料を「どう読めばいいのか?」という視点から、歯科医院の院長先生向けに読み解き方のポイントをお伝えします。
「木を見て森を見ず」にならないために
議事録や資料を読み始めると、歯科に関する言及が少ないと感じるかもしれません。実際、財政制度審議会や中医協で議論される中心は、病院や医科領域です。歯科はその一部に過ぎず、改革全体の流れの中で位置づけられているのです。
たとえば、2025年に予定される令和8年度の診療報酬改定に向けて、財務省が「歯科無床診療所の利益率が高い」と主張しています。この動きの背景には、医療費全体の抑制という政府の大きな方針があります。つまり、歯科の制度は常に「森」=社会保障改革の一部として設計されているのです。
読む順序と観点を押さえる
審議会資料、改定に向けた動きを読む際は、以下のような順序と観点を意識することをお勧めします:
1.財政制度審議会の建議(意見書)や経済財政諮問会議の資料
→ ここで国の「財政的な制約」や「改革方針の全体像」が提示されます。たとえば「医療費は自然増を抑え、ICTや連携で効率化を図るべき」というメッセージが強調されます。
2.各種専門部会、医療保険部会、中医協での議論資料や個別論点整理資料
→ 診療報酬の細かな改定点(訪問診療、口腔機能管理など)が扱われます。
3.過去の改定資料の振り返り
→ 過去にどのような項目が削減・強化されたのかを見ることで、将来の改定方向を予測できます。
4.マスコミによるネガティブキャンペーン
→診療報酬改定の前には特定のマスコミが医療機関のネガティブキャンペーンをしますが、その内容によって翌年の改定の重点が見えることがあります。
5.各政党の主張や動き
→今年の様に国政選挙がある場合には結果が改定の方向性や改定率に影響を与えます。
6.医師会や医系議員の動き、首相官邸や財務省、厚生労働省との駆け引き
→12月の改定率決定に向けて動きが活発になっていきます。
「面倒」と思われましたか?
私の様に40年以上も情報を追いかけている人間と違って、院長にはそんな時間は無いかもしれません。
なので、この経営ブログでも少しづつ紹介していきますね。
改定の舞台裏:政治的駆け引きと「見えない力」
診療報酬改定は単なる「技術的調整」ではありません。実際の改定率は、年末にかけての「首相官邸⇔財務省」 vs 「与党医系議員・医師会・厚労省⇔首相官邸」の駆け引きの中で決まることが多いのです。
この駆け引きの構造を知ることで、「今出ている案がそのまま通るとは限らない」という視点を持つことができます。特に令和8年改定においては、参議院選挙の結果がこの駆け引きに影響を与えると見られています。
維新の会や国民民主党が躍進すれば令和8年の診療報酬改定はより厳しいものになるでしょう。
政策資料の活用で医院経営の精度を上げる
例えば、在宅歯科医療に関する議論では、「訪問回数ではなくアウトカム(成果)で評価すべき」との主張が強まっています。これは、「何回訪問したか」ではなく、「患者の状態がどう改善したか」が評価軸になってくるということです。介護の分野にも科学的介護の視点が導入された様に、国の予算の使い方もエビデンスがあるものへの投資という方向性が強まっているのです。
こうした変化を事前に読み取り、訪問診療の記録や医科・介護職との連携体制を整備しておくことが、将来の医院の報酬維持に直結します。ICTやデジタル基盤整備もいずれは避けて通れない様になりますので、どのタイミングで取り組むのかの判断が院長に求められるのです。
院長が担うべき「読み解き力」と「問いかけ力」
これからの院長に求められるのは、国の社会保障政策と政策資料を読み解く「政策読解力」と、スタッフに問いかけ、行動を促す「リーダーシップ力」です。
読み始めの段階では難解に感じるかもしれませんが、まずは「知らない言葉を調べる」ことから始めましょう。繰り返すことで、次第に改革の方向性や流れがつかめるようになります。診療報酬改定は、単年の変化ではなく、長期的なビジョンのもとで「点」と「線」がつながっていく構造です。過去からの医療改革の流れの先に未来があり、その政策を実現していく為に診療報酬改定があるのです。
流れで見れる様になれば「口管強基準」の意味も分かりますし、改定で何もしなくても算定できる点数だけ取るなんてことは無くなるはずです。
先生の医院では、次の診療報酬改定に向けて、どのような準備を進めていますか?
令和6年の診療報酬改定にさえ対応できていないのなら早く対応していくことをお勧め致します。
令和8年診療報酬改定に向けてどう準備をすればよいのかが分からないのならご相談くださいね。