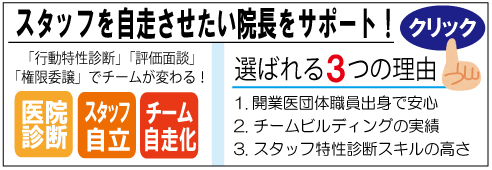地域包括ケアの時代における歯科医院の新たな使命
近年、地域包括ケアシステムの進展により、歯科医院に求められる役割が大きく変わりつつあります。特に、医科・薬局・介護施設・学校、行政など、他職種や他機関との連携が歯科医療の質向上に直結する時代になりました。
高齢者施設や病院での口腔ケアや口腔機能回復が、誤嚥性肺炎の予防や栄養状態の改善に大きな効果を発揮することが明らかになる中で、地域の「かかりつけ歯科医」としての役割が再評価されています。単に「治療する場所」としての医院から、地域の健康を支える「多職種と連携する医療拠点」へと進化していくことが、今後の歯科医院の競争力にも直結していくでしょう。
「噛めない」ことが引き起こす連鎖的な健康課題
要介護者や高齢者において「噛めない」「飲み込めない」といった口腔機能の低下は、見逃せない健康リスクです。食事が思うように摂れなくなることで低栄養状態に陥り、さらには誤嚥性肺炎や身体的なフレイル、社会的な孤立などを引き起こします。
このようなリスクに対処するには、医師・看護師・介護職・管理栄養士、理学療法士、言語聴覚士といった他職種と歯科医院が連携し、早期に対応していくことが不可欠です。特に、訪問歯科や施設での口腔ケアを担える体制を整えておくことで、地域から信頼される「歯科の拠点」となることができます。
先生の医院では、高齢者や要介護者への対応について多職種とどのような連携を行っていますか? 一度、スタッフと共有し、見直してみてはいかがでしょうか。
現場で進まない「地域連携」の背景と課題
とはいえ、実際には地域の多職種としっかりと連携している歯科医院はまだ少数派です。「か強診」の施設基準も、訪問診療を理由に取得を見送るケースが多く見られました。それは「口管強基準」となっても同じです。訪問要件は大幅に緩和されましたが、「いま経営的に何とかなっているから面倒なことには取り組みたくない」と考える小規模歯科医院の院長もまだ多いのです。
また、医院規模が大きくなってきても訪問や連携に積極的に取り組むかどうかの判断は院長によって分かれます。
何故なら外来診療と訪問の両立には相応の仕組みづくりが求められるからです。たとえば、訪問専任の歯科衛生士の配置や、医科・介護施設との連携スキームを持つ地域連携担当者の設置など、戦略的に体制を整えることが必要です。最初は外来との兼任から始めるとしても、外来さえもマンパワー不足に陥り易い時代に両方を成立させるハードルは高いのです。
今は「歯援診への紹介」という連携も可能ですので、ご自分の医院で可能な連携方法について考えていくことが必要だと感じます。先生の医院の「かかりつけ患者」が病院に入院した時、歯科医療は途切れていないでしょうか?患者にとって必要な歯科医療を連携によって繋いでいくことも歯科医院に求められる役割だと感じるのです。
経営資源は有限。選択と集中が戦略になる
中小規模の歯科医院にとって、人的・時間的な経営資源は有限です。だからこそ、すべての制度要件に対応しようとするのではなく、「何に注力するか」「どの地域ニーズに応えるか」を見極めることが重要です。
たとえば、訪問診療に強みを持つ医院は、地域包括ケアシステムの中心的役割を担うことで、安定した患者層を確保できます。一方で、院内の小児・障害者対応や生活習慣病患者への治療、口腔機能回復、口腔ケアに注力することで、医科との連携を深めるアプローチも可能です。選択と集中によって、限られた資源でも高い医療価値を提供できるのです。
これからの歯科経営に求められる「医療視点」とは?
地域連携を通じた医療の質向上は、単なる制度対応ではなく、「患者の生活全体に関わる医療」を実現するための大切な視点です。高齢者や障害者、有病者といった今後さらに増加するであろう患者層とどう関わるかは、医院の未来を左右する問いとも言えます。
先生はどうお考えですか?
国が歯科医院に求める役割を果たすことで経営を成立させていくべきでしょうか?
それとも、診療報酬的には優遇されなくても新たな歯科医療需要には踏み込まないという選択肢もあるかもしれません。
地域に選ばれる歯科医院となるためには、制度の変化を先取りしながら、自院の理念と整合する形で「医療の質」を再設計していくことが求められているのです。
ひとつ明確に言えることは、保険医療制度と診療報酬体系は、国によって今後も計画的に変化させられるということです。今年はすでに令和8年診療報酬改定に向けた前哨戦が活発ですので、年末に向けて表と裏での激しい攻防戦が繰り広げられるでしょう。
もちろん、この夏の参院選の結果も改定率の決定に影響を及ぼします。
そして現状では大幅なプラス改定は考えにくい。
その中で多くの院長には、保険医療機関の的確な経営の舵取りが求められるのです。