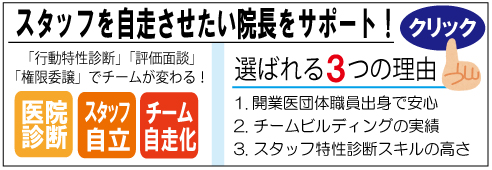今日から、歯科医院の成長に必要な業務改善の「5つの視点」について、以下のテーマで掘り下げていきます。
1.オペレーション視点(業務効率化)
2.患者視点(サービス向上)
3.歯科医療としての視点(医療の質)
4.5S視点+安全視点(職場環境・感染対策)
5.マーケティング視点(集患・認知・ブランディング)
なぜ今、「業務の標準化」が必要なのか?
中規模の歯科医院となり、スタッフ数も15〜30人と増えてくると、「誰が、いつ、どのように行うか」が曖昧なままでは、日々の診療品質や患者対応にばらつきが出やすくなります。シフトで人が入れ替わったり、急な欠員が出たり、ベテランが退職して新人に変わることは珍しくありません。
そんなときに大切なのが「業務の標準化」と「マニュアル整備」です。属人化を防ぎ、誰が行っても一定の品質を保てる状態を作ることが、安定的な医院運営の土台になります。これは単なる効率化ではなく、「医院ブランドを体現する仕組み」を作ることでもあります。
先生の医院では、受付対応やアシスタント業務の品質基準をスタッフ全員が共通理解していますか?
マニュアルは「教えるツール」であり「進化する仕組み」
マニュアル整備というと、紙に印刷された静的な手順書をイメージされるかもしれません。しかし、現在はそれだけにとどまりません。ナレッジ管理のデジタル化、動画マニュアルや業務フローチャート、チェックリスト、患者説明ツール、育成カリキュラムなど、目的に応じた「複合的なマニュアル」が求められます。
例えば「新人受付スタッフが1ヶ月以内に基本業務を一人でこなせるようになる」ことを目標とするなら、段階的なトレーニング計画と、日々のチェック項目、そしてOJT担当者の明確化が必要です。ここで重要なのは、マニュアルが「伝えるためのツール」であると同時に、「育成や品質維持の基準」であるという点です。
また、マニュアルは作ったら終わりではなく、常に診療の現場や患者対応の変化に合わせて見直し、アップデートしていく必要があります。これはまさに「仕組みの進化」であり、業務改善の真髄といえるでしょう。
ブランドコンセプトとオペレーションは連動している
よくあるのが、歯科医院のホームページでは「丁寧で安心の診療を提供します」と謳っているにもかかわらず、実際は保険診療を高速で回すオペレーションで、患者が質問しにくい雰囲気になっているケースです。
これは、医院のブランドコンセプトと実際のオペレーションが一致していない典型例です。高級ホテルと簡易ホテルではサービス設計が違うように、歯科医院でも選択する収益モデルと目指す価値によって設計すべきオペレーションは異なります。
もし「一人ひとりの患者様としっかり向き合いたい」という理念を掲げるのであれば、アポイントの取り方からスタッフ配置、説明時間の確保までを含めた全体設計が必要になります。つまり、「どういう医院を目指すのか」という上位概念と、「日々のタスクの回し方」がつながっている必要があるのです。
また、オペレーション設計によって必要な人員数が変わり残る利益が変わります。
実際に同じ売上を上げるのに人員数が2倍近く違うというケースもあるのです。
オペレーション品質の見える化とチェック体制
院長先生ご自身が診療に集中されていると、医院全体のオペレーション品質が劣化していても気づきにくいことがあります。実際に私が医院見学をすると、「患者視点では気になる点」がいくつも見つかるケースは少なくありません。
そのためには、まず「チェックする視点」を明確に持つことが大切です。たとえば以下のような視点でマニュアルやチェックリストを整備していきます。
・患者視点(受付対応、説明のわかりやすさ)
・連携視点(スタッフ同士の連携・引き継ぎ)
・医療品質視点(診療の正確さ、技術手順)
・安全性視点(滅菌・消毒、動線)
・生産性視点(無駄な待機や移動の削減)
そしてそれぞれの視点において、医院内で一番スキルの高いスタッフが評価を行い、改善点を共有する体制をつくることが、質の維持・向上につながります。
標準化は医院成長の「イロハのイ」
タスクを標準化し、マニュアルを整備することで、初めて「医院としての品質」が定義され、維持・進化していく準備が整います。受付対応、診療アシスト、消毒・滅菌、光学印象や写真撮影、患者説明、さらには電話対応に至るまで、すべての業務において「この医院の基準とは何か?」を言語化・可視化することが求められます。
これは簡単なことではありませんが、だからこそ取り組む価値があるのです。そして、そこに取り組む医院こそが「理念を体現する組織」となり、患者・スタッフ双方から信頼される存在になっていくのです。
先生の医院では、理念をオペレーションにどう落とし込んでいますか?
今あるマニュアルや業務の仕組みは、それを表現できるものになっているでしょうか?
次回は、業務改善の第二ステップ「院内の情報共有の仕組みづくり」についてお伝えしていきます。チーム全体が同じ方向を向くための情報の流れと、共有文化の育て方について掘り下げていきます。
どうぞお楽しみに。