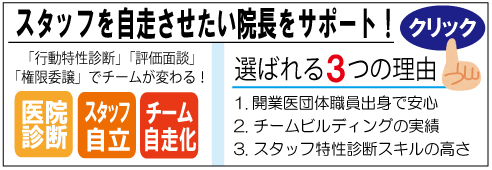現時点ではSNSだけで新患を多く増やすことは出来ません。
しかし、SNSなしでは“選ばれる理由”を証明できない時代に移行しつつあるのです。
「SNSを頑張れば新患が増える」
そんな時代は10年前に終わっています。
今のSNSは
患者が来院前に“医院が本物かどうか判断する”ための根拠集めです。
GoogleAIオーバービューでも、
“継続的な専門性の発信”を強く評価するようになっています。
だからこそ歯科医院は、
“派手さではなく信頼の一貫性”を発信する必要があるのです。
1.SNSが必要な理由は「集患」ではなく「リスク回避」
患者は来院前に必ず確認します。
・院内の雰囲気は嫌じゃないか
・スタッフは丁寧そうか
・治療が怖くない医院か
・この医院は“安全”なのか
つまりSNSは“入口”ではなく
医院の安全性・信頼性を証明するための“出口”コンテンツ
なのです。
SNSが空白の医院は、
患者から見ると「情報がない=不安」です。
2.専門性の発信は「難しい内容」ではなく「身近な安心感」
GoogleAIは、過剰に専門的な投稿より、
“患者が理解できる言語での専門性” を高く評価します。
例)
・歯周病の状態が改善した“理由”を図解
・歯科衛生士によるケアの“意味”を説明
・予防のメリットを“行動に焦点を当てて”発信
・院長の治療方針をやさしく言語化
専門用語でなく、患者の行動が変わる説明が評価されます。
3.SNS発信で最も大事なのは“医院の雰囲気”の可視化
患者が本当に見たいのは
・チームの雰囲気
・治療中にどんな声かけをしているか
・歯科衛生士がどう寄り添うか
・院内の“空気感”が安心かどうか
ところが、多くの歯科医院はここでつまずきます。
■ つまずき①:スタッフが発信できない
・文章が書けない
・写真の構図が苦手
・続かない
・フォロワーが増えないからやる気が出ない
■ つまずき②:顔出しNGが多く、雰囲気が伝わらない
・スタッフの表情が出せない
・動画も出せない
・結果として“何も伝わらない”アカウントに
これは多くの医院が抱える問題です。
4.では、何を発信すべきか?
王道のSNS戦略の答えは一つです。
①治療品質の見える化
②医院の価値観の見える化
③スタッフの専門性の見える化
これさえ出来ていれば十分です。
難しく考える必要はありません。
▼ 投稿テーマ(歯科医院SNSの王道)
① 専門性(患者が理解できる言葉で)
・歯周病の改善例(個人情報配慮)
・歯科衛生士によるプラークコントロールの成果
・インレー/クラウンではなく治療法の選び方(簡潔に)
・予防の効果を数値で説明
② 治療方針の透明性
・「この医院が大切にしている診療姿勢」
・「どんな患者さんに支持されているのか」
・「治療の流れをわかりやすく」
③ チームの価値観
顔出しNGでも投稿できます。
例)
・受付スタッフの“声かけの工夫”
・DHの“担当制へのこだわり”
・アシスタントが治療をスムーズにするための工夫
・院内ミーティングの一部を引きの写真or写真なしで紹介
写真なしでも“価値観の文章コンテンツ”は強いです。
本格的に活用できれば強い発信力を得られるSNSですが、実際には中途半端なままで効果を出せない医院が多いと感じます。
では、そんな医院でも実行可能な活用法はないのでしょうか?考えてみます。
5.SNSが苦手でもできる“最低限の発信設計”
ここが院長の本音の悩みだと思います。
✓ スタッフが誰もSNSを続けられない
✓ 顔も名前も出せない
✓ 投稿しても伸びない
✓ 頑張っても新患が増えない
このような医院がとるべき方法は
【最も現実的で効果が出るSNS活用法】
① 院長が“文章投稿”を週1で書く
→ 写真不要、顔出し不要
→ 価値観・治療へのこだわりを書くだけでOK
→ Google評価も最も高い形式
② 歯科衛生士は“患者が明日からできる1つの行動”だけ投稿
例)
・「デンタルフロスは“夜だけ”で十分」
・「磨き残しが多くなる人の共通点」
※文章だけでOK
※専門性評価が高まる
③ チームの価値観を“文字投稿”で発信
写真も動画もいりません。
例)
「治療中、患者さんの不安を下げるために気をつけている3つのこと」
④ 投稿フォーマットを全員で統一
例)
①結論
②理由
③明日からできる行動
これだけで“医院の知性”が伝わります。
⑤ “流入目的”のSNS運用はやめる
→ 歯科医院SNSは“選ばれるための安心材料”
→ 新患はSNSではなくGoogle経由で来ます
→SNSはブランド構築・価値観の可視化ツール
6.まとめ
SNSは「派手さ」ではなく「信頼の一貫性」で評価される
GoogleAI オーバービューはこう評価します:
・専門性
・一貫性
・透明性
・患者の理解を促す発信
つまり、
文章だけでも十分に“選ばれる医院”を証明できる時代です。
「スタッフがSNSできない」
「顔を出せない」
「写真が苦手」
そんな医院でも大丈夫。
文章だけでも、価値観の可視化だけでも、
発信の質さえ正しく設計されていれば評価されるのです。
 |
|
 |
|
 |