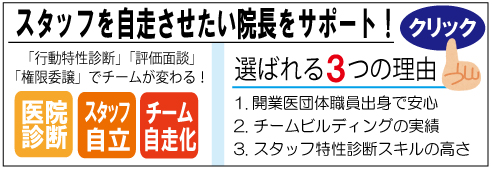おはようございます。
歯科医院経営コーチの森脇康博です。
今日から新シリーズ開始です。
最初のテーマは「診療報酬と地域社会の変化が歯科医院経営に与える影響とは?」で、 今日は「地域人口動態(高齢化・人口減少)を把握する簡易分析手法」について書きたいと思います。
なぜ「地域の人口動態分析」が歯科医院経営に不可欠なのか?
近年、診療報酬の改定と地域医療構想の方向性を見ていると、国が求める歯科医院の役割が大きく変わりつつあることが分かります。 とくに、「高齢化対応」「在宅歯科医療」「地域包括ケアへの参画」などが重視される中で、 地域の人口構造を正確に把握しておくことが、医院の経営判断に直結する時代になりました。
令和8年の診療報酬改定では、地域における医療資源の最適配置と「訪問・重症化予防・ICT」の活用が評価される方向です。 その一方で、無床診療所(歯科を含む)の「過剰利潤」論や、ベースアップ評価料の「届出していない=余力がある」論など、 厳しい視点で診療報酬のマイナス改定を主張する声もあります。
では、先生の医院が位置する地域は今後どうなっていくのか?その変化に合わせて医院はどう適応すべきなのか? まずは地域の「人口動態」という足元の情報を丁寧に読み解くことが第一歩です。
自院の地域における「人口構造」を知る3つの簡易ステップ
1. 自治体の統計データを確認する(5分)
市区町村のホームページや「国勢調査」「将来推計人口」の公開データを確認。 65歳以上の高齢者割合、15歳未満の子ども、将来予測などをチェックします。
2. 診療圏人口と競合の確認(10分)
自院から半径1〜3kmの診療圏人口や競合医院の数・規模を把握し、地域内のポジショニングを確認します。
3. 患者層とのギャップを探る(15分)
来院患者の年齢層と地域人口構造に差がないか分析。高齢者が多い地域で若年層中心の運営をしていれば、 ニーズを取りこぼしている可能性があります。
先生の医院では、地域の年齢構造や将来人口予測をスタッフと共有したことはありますか?
実例:郊外型歯科医院の判断を変えた「人口ピラミッド」
ある郊外型の歯科医院(ユニット6台・スタッフ15名)は、以前は若いファミリー層向けの予防歯科を主軸にしていました。 しかし、地域自治体の将来人口予測により「高齢者比率35%超」が明らかになったことを受け、経営方針を転換。
・口腔機能評価の研修を受け実績のある医院を見学し、フレイル予防プログラムを構築
・訪問歯科の実績がある歯科医院をスタッフと一緒に見学。訪問歯科の経験がある歯科衛生士を採用。
・知り合いの介護施設の経営者と連携し、現場ヒアリング・見学の実施
・多職種連携の場に参加し、共同で連携フローチャートを作成
・在宅訪問歯科の体制構築とICT記録に向けて取組みをスタート
その結果、 地域の現状と診療報酬改定の方向性にもマッチした経営展開の準備が整いました。
人口変化を「見える化」してチームの方向性を揃える
人口構造の変化は医療ニーズと価値観に影響を与えます。 2025年以降、団塊世代が後期高齢者に移行する中で、患者ニーズや意思決定も変わっていきます。
ターゲットを子育て層にできる地域もまだありますが、子育て層を惹きつけられるだけの魅力を医院が表現出来なければ経営面で苦戦することになるのです。
だからこそ、院長一人で統計を眺めるのではなく、 「私たちの医院がこの地域で何をすべきか?」をスタッフと一緒に考える時間が重要です。
経営者として、次に何をすべきか?
人口動態を定期的に把握し、経営判断に活かすことで、 政策変化に流されず先手を打てる医院になります。
地域人口データをもとに、今後3年・5年の診療モデルの再設計は進んでいますか?
より詳細な「診療圏分析」や「地域医療構想との整合」を知りたい方は、 「経営環境分析」へお申し込みください。